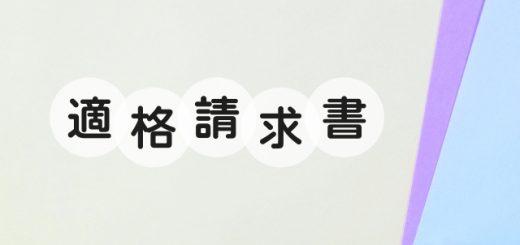一時払い終身保険は節税になる?個人の場合の答えと注意点
一時払い終身保険は節税になる?
高齢者が節税対策のために一時払い終身保険に加入するのは珍しくありません。一時払い終身保険とは、契約時に保険料を一括で払うと、保障を一生涯受けられる生命保険のことを指します。つまり、解約しない限り、万が一のことがあったときにまとまった保険金を受け取れる仕組みです。
税金の面から見た一時払い終身保険のメリットとして、死亡保険金の非課税枠を活用できることが挙げられます。前提として、生命保険の契約者が死亡した際に遺族が受け取る死亡保険金は、相続財産ではありません。しかし、みなし相続財産として扱われるため、相続税の基礎控除とは別に非課税枠が設けられています。「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となるため、法定相続人が2人だった場合は1,000万円まで相続税がかからない計算です。つまり、同じ1,000万円でも、現金や預貯金として残すより、あえて保険金として残すほうが節税できます。
また、相続税がかかりそうな場合は、死亡保険金を受け取れる状態にしておくことで、納税資金を確保することが可能です。死亡保険金は相続人個人の財産として扱われるため、遺産分割協議が成立していない状態でも、保険会社に請求できます。つまり、早い段階である程度まとまった資金を確保できるのが大きなメリットです。
ただしこんな落とし穴もある
既に触れたように、一時払い終身保険を契約することには、節税や納税資金の確保という意味で一定のメリットはあります。しかし、細かい注意点もあるため、事前に考えてから使いましょう。
まず、生命保険の非課税枠を使うためには、死亡保険金を相続人が受け取らなくてはいけません。相続人以外の人が受取人になる場合は、非課税枠が使えないうえに、相続税を相続人より多く支払うことになります。さらに、非課税枠は相続人の数によって決まるため、保険金が高額すぎるとあまり節税にならないのも事実です。
また、契約者と受取人の関係によっても税金が異なる点にも注意しなくてはいけません。例えば、契約者と被保険者が同じ、受取人が相続人であれば相続税が課税されます。この場合、相続税の非課税枠やみなし相続財産の非課税枠を利用することが可能です。しかし、契約者と受取人が相続人で、被保険者が被相続人という場合、あくまで保険料を払っているのは相続人に過ぎません。つまり「自分で払った保険料を増やして保険金をもらった」という意味になるため、増えた部分に対して所得税を払います。つまり、相続税の非課税枠やみなし相続財産の非課税枠は使えません。
さらに、死亡保険金は相続財産に含まれないため、相続人の誰か1人が高額な死亡保険金を受け取る形になっているとそれ以外の相続人とのトラブルの火種になります。
いずれにしても、一時払い終身保険が本当に節税になるかは、その人が置かれた状況による部分もあるので、まずは税理士に相談してみましょう。